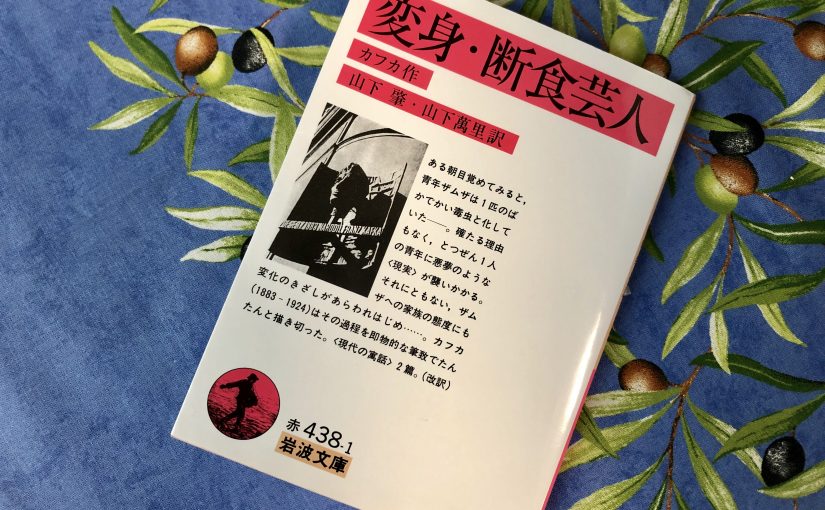
『変身』(岩波文庫)
ななちがカフカの『変身』を読んでみたいと言い出した。国語の教材に冒頭の一文が引用されていて、一体どんな話なのか続きがものすごく気になったらしい。(まあそうだろうな…。)そんな訳で早速アマゾンでポチり、私も久しぶりに読み返してみた。
高校時代に読んだ際には「気持ち悪さ」だけが残った。身も心も毒虫化していくグレゴールの描写も、グレゴールの死によって迎えるハッピーエンド的な描写も、全てが気持ち悪くて不快だった。
あれから時が経つこと25年。当時感じた気持ち悪さは、見えないふりをしていたものを見せられた時に感じる居心地の悪さなのだということに気がついた。
大黒柱として働いていたグレゴールが突然毒虫になってしまった時、家族は彼に降りかかった不幸を嘆いて憐れむが、その存在が次第に家族のお荷物になってくると、彼を疎ましく思うようになる。やがて自分たちの生活に害をなすようになってくると、家族はその死を願うようにすらなり、最後には彼の死を祝って家族旅行へと出かける。
この家族の仕打ちは冷酷に見えるが、こうした事は現実社会の中でも実際に起こっている。介護現場やひきこもり問題、きょうだい児の苦悩など、社会の中には綺麗事ではすまされないことが多くある。カフカは人間のそうした黯い一面を「毒虫」というメタファーを用いて描いたのだと思う。
今回購入した岩波文庫版の『変身』にはもう一編『断食芸人』という短編小説が綴じられている。一世を風靡した断食芸人が、より技を極めようと長期の断食に挑戦するが、人々は新しい娯楽に夢中になり芸人に対する興味を失っていく…といった内容で、想像通りのバッドエンドで結ばれる。悲惨な話だが、似たような事は現代社会でも起こっている。
人間の冷酷さや醜さをありのままに見せつけられると、陰鬱な気持ちになる。自分の中にもそうした部分があるということに気づかされるからだ。しかしそれを受け入れ「自分も含め人間には冷酷で醜い部分もある」と認めてしまえば、楽になると思う。過度な期待をしなくなる分、人に寛容になれるし、自分の事も愛しやすくなるからだ。
高校時代には気持ち悪さしか残らなかった『変身』だが、今回は気持ち悪さと共にバツの悪さと小さな安堵感も残った。
2019.10.30投稿

